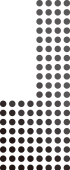「東京コレクション」ライナーノーツ
2004年9月8日、デビューシングル「群青日和」で豪雨の新宿を描くことから始まった東京事変。前年秋の椎名林檎ソロ・ツアー「雙六エクスタシー」のメンバーがそのまま移行する形でバンド活動へと雪崩れ込んでいった経緯は、初めて聞かされた時、もちろん大きな違和感があった。過去のソロ作でも、椎名は曲ごとのプレイヤー・クレジットにバンド名を与えていたし、実際に発育ステータスという5人組バンドでツアーを行ったことからも、彼女が常にバンドに対して憧れを抱いていたことは周知の通りであった。しかし、好調を極めていた当時のソロ活動を一時的に休止してスタートさせた東京事変の活動は、リスナーはおろか、椎名本人も恐らくはその行方が分からなかったはず。しかし、それでも彼女の音楽人生をかけて、賽は投げられた。
そんな、ある種の逆境から始まった彼らの活動は、キーボーディストのH是都MことPE'Zのヒイズミマサユ機とギタリストの晝海幹音ことヒラマミキオの脱退、浮雲と伊澤一葉の加入を経て、気が付けば、5枚のアルバムと最新作『color bars』が7年の軌跡を鮮やかに描き出すに至った。椎名個人でいえば、さらなる音楽性の真価と成熟を鳴らすために、東京事変での活動が必然であったことに疑う余地はなく、彼女にとっての必然の音楽はリスナーの日常にゆっくりと溶け込んでいった。そして、当たり前のように活動が続いていくものだとさえ感じられていた矢先にもたらされた解散の一報。驚きと喪失感の大きさは、東京事変の音楽に芽生えたリスナーの愛情を物語る。そう、彼らは7年の活動を通じて、多くのリスナーの音楽風景を塗り替えてしまったのだ。
しかし、同時に、恐らくはこれ以上ない達成感を感じたからこそ、そして、それぞれが個々の活動の更なる充実のために、彼らが大人のバンドらしい決断を下したであろうということもまたよく分かる。思春期的な感情をこじらせることもなければ、崩れてしまうこともよしとするようなロックの美意識に固執することもない、あまりに潔い決断。それは、最新作、そのタイトルにテレビの放送終了後に映し出される『color bars』を持ってくる去り際の美しさ同様、見事というしかない。そして、終わったはずの放送、東京事変を構成するメンバーそれぞれの個性というcolor barsが音のみの長編ライヴ・ドキュメントを映し出す。それが本作『東京コレクション』だ。
圧倒的な手数から生み出されるグルーヴで曲をドライヴさせる刄田綴色のドラミング。カントリーからジャズ・ファンクまで、トリッキーなプレイで弾き分ける浮雲のギター・プレイ。他アーティストのプロデュースやアレンジだけでなく、このバンドにおいてはアップライト・ベースからスラップまで、自由自在に操るベース・プレイヤーとして、はたまた、ソングライターとしての評価をも確立した亀田誠治。キーボードとギターを巧みに使い分けながら、理知的なアレンジメントとエレガントなプレイが耳を惹きつけてやまない伊澤一葉。そして、ヴォーカリスト、ソングライターとしてのさらなる飛躍に加え、リアルタイムで刻々と変化するバンドの現場でミュージシャンシップの高さを発揮した椎名林檎。脱退しても記憶に残る晝海幹音の美しい憂いを帯びたギターとH是都Mが鍵盤上を猛烈な勢いで走らせた指先。
それぞれ超一流の才能の持ち主である5人が曲を持ち寄り、レコーディングとライヴを重ねることで、束の間のセッションでは到達し得ない音楽の高みへと上り詰める。その幸福な瞬間が本作『東京コレクション』には間違いなく詰まっている。最後に残された新曲「三十二歳の別れ」から時を巻き戻すかのように、最初期の一曲「夢のあと」へ。そして、走馬燈のようによみがえる、曲にまつわる聴き手それぞれの記憶や思い。アルバムを聴き終え、なんだ、夢落ちか。そう思うかもしれない。しかし、音は止んでも、耳にはひりひりした切なさと明日を切り開く言葉の確かな残響がいつまでも残り続ける。
東京事変にさよならは言えても、その音楽にさよならをいう方法はいまのところ見つからない。
(小野田 雄)