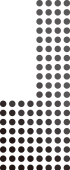「大発見」ライナーノーツ
それにしてもとんでもないアルバムである。何度リピートして聴いてもなお、つくづくそう思う。
これまでも幾つかの媒体で書いてきたが、東京事変とは極めて希有なバンドだ。椎名林檎という驚異的な才能を持ったアイコンを中心に、浮雲、伊澤一葉、亀田誠治、刄田綴色という、世代も個性も異なる4人のメンバーがそれぞれの人格をバンドに持ち込んでいる。一見理想的なシンフォニー(交響曲)のようで、その実は時に危うい、非常に希有なバランスのポリフォニー(復音楽)みたいな音楽家集団なのである。
「教育」にはじまり、「大人」、「娯楽」と、彼らはチャネル設定というコンセプチュアルアートのような制作形態によって、アルバム毎にさまざまな音楽実験を繰り広げてきた。それでいて、『あくまでも私たちが作るのはポップスである』(椎名)とポピュラリズムの探求も忘れない、特異なハードル設定によって活動を続けてきたのだ。そんな五人にとって、前作『スポーツ』とツアー『ウルトラC』は、まさにスポーツさながらのマッシブで躍動感に満ちたバンドサウンドと、徹底的なまでのライブにおける再現によって、バンドにとっての“金字塔”となった。
「筋肉であり躍動であり、お客さんとの対話における運動性を学びましたね」(椎名)
「心身共にすべてを出し切った。苦労もあったけど、その分バンドとしての“絆”は確実に深まった」(亀田)
その後TVドラマの主題歌(「天国へようこそ」)や椎名自身がキャラクターを務めるCMタイアップ(「ドーパミント!」、「空が鳴っている」、「女の子は誰でも」)という、自らの存在を広くお茶の間レベルへとアピールするチャンスを経て、東京事変は1年4カ月振りに待望のニューアルバムをリリースする。
タイトルは『大発見』。英訳表記は“Discovery”。本作はチャネルマナーこそ踏襲(=ディスカバリー・チャンネル)しているものの、たとえば“スタンダード”、“プリミティブ”、“バック・トゥ・ルーツ”といった多くのセンテンスを内包している点など、これまでのアルバムとはいろいろと様子が異なるのだ。
「まず選考にかける以前で、自分自身がハッとする、つまりは“発見”する曲でなくてはならなかった」(椎名)
“大いなる発見”というテーマの下に集まった楽曲は既記のシングルを含む全13曲(+ボーナストラック1曲)。刄田以外の4人が作曲クレジットに名を列ね、しかもうち5曲は共作曲である。
「すべての曲を『大発見』にするために、全員の持っている力を総動員した結果、自然と共作が多くなった」(亀田)
だがそれでいていずれの曲も、作者の個性だけが強く前に出過ぎることがない。
「クレジット上では椎名さんと誰かという表記でも、今回はすべての曲に事変全員としての共作感がある」(浮雲)
また本作には「電気のない都市」という、3.11の東日本大震災後を想起させる楽曲が収録されている。誰もが生死を意識した3月の体験は、無論椎名の心にも様々な想いを去来させていたのだ。
「震災後の計画停電で、さいたま新都心の、スーパーアリーナを含むその周辺の灯りがすべて消えてしまっている光景を見たら、急にイントロのピアノが聴こえてきて、この曲が唄として完成しました」(椎名)
学問と遊戯。自然と文明。男と女。大人と子供、現在過去未来。そして陸(都市)海空に風と、その上の天国。楽曲タイトルには我々が過ごす日常のすべてがあり、まるで営みのあらゆる場面において聴くことのできるアルバムとなるようにといった願いが込められたかのようだ。
「完成しても未だ、自分でも驚くほどピュアな感情の行き来が絶え間なく続いている」(伊澤)
「このアルバムには去年から今年の、それこそ震災前後も含めた濃密な時間が詰まっている」(亀田)
「ツアーではたとえBPMの速い曲でも、かけがえのない曲だからこそ、噛み締めるように弾きたい」(浮雲)
「出たとこ勝負でも絶対いいライブになる。そう言えるだけのアルバムになりました」(刄田)
「私たちの営み、事変のこれまで、そのすべてを詰め込みたかった。多くのリスナーに聴いて戴きたい反面、そっと閉じ込めたままにもしておきたい。初めてそんな気持ちを抱いた、宝箱のようなアルバムになりました」(椎名)
アフロやグラム、ジャズにビートパンクやシャンソンといった様々な音楽のエッセンスを擁し……と書くのは容易いがそれじゃ間に合わない。ロックかポップスかといった話も最早鬱陶しいだけだ。『スポーツ』がバンドにとっての金字塔だったとすれば、『大発見』はまさに2011年の邦楽全般における金字塔となる。筆者はそう信じている。
(内田正樹)